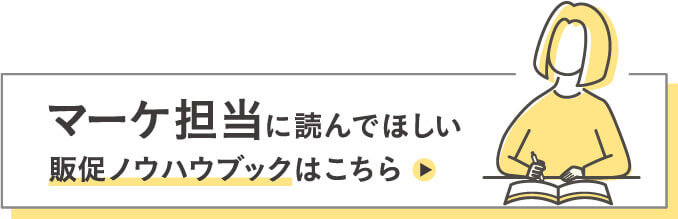マーケティング心理学 |カリギュラ効果と希少性マーケティング

禁止されるとかえって興味が湧く『カリギュラ効果』とは?
人は「やってはいけない」と言われると、かえってその行為に興味を持ち、惹きつけられることがあります。これが『カリギュラ効果』と呼ばれる心理現象です。
この名称は、1980年に公開された映画『カリギュラ』に由来します。内容の過激さゆえに一部地域で上映禁止となったことで、逆に観客の興味を大きく集め、ヒットにつながりました。「禁止されたからこそ見たくなる」という心理が働いたわけです。マーケティングの世界でも、このカリギュラ効果は活用されています。
【使用例】
再春館製薬の「ドモホルンリンクル」のTVCMではないでしょうか?上品なトーンではありますが、冒頭のメッセージは「初めての方にはお売りできません」といきなり新規顧客の購入を禁止しています。しかしその後に「売れないわけ」と「買うためにはどうすればいいか」が丁寧に説明されています。年齢化粧品を求めているターゲットに対して圧倒的な印象と自発的な好奇心を与えている、「カリギュラ効果」をうまく効かせています。
【カリギュラ効果を使う際の注意点】
あまりにも頻繁に「禁止表現」を使うと、消費者は慣れてしまい効果が薄れていきます。また、過度な演出は誇張表現や信頼低下につながる恐れもあります。カリギュラ効果はあくまで「禁止されるからこそ興味が湧く」という人間の心理を自然に刺激する演出として、適切な場面で活用するのがポイントです。
併用される『希少性マーケティング』とは?
カリギュラ効果と並んでよく使われる心理テクニックが希少性マーケティングです。これは「数量が限られている」「期間が限定されている」と伝えることで、人の「逃したくない」「今すぐ欲しい」という心理を刺激する手法です。
・「先着100名限定」
・「今月末までの期間限定セール」
・「数量限定モデル」
といった表現はまさに希少性マーケティングの典型例です。「手に入りにくいものは価値が高い」と感じる人間の心理を活用しており、特に販売促進やキャンペーン施策で高い効果を発揮します。
カリギュラ効果と希少性マーケティングの違い
どちらも「今すぐ行動したくなる心理」を刺激する点では共通していますが、カリギュラ効果は“知りたい”心理、希少性マーケティングは“欲しい”心理に訴えかけるのが大きな違いです。
【カリギュラ効果】
心理の起点 :禁止・制限で興味が湧く
刺激する感情:好奇心・反発心
主な表現 :「閲覧注意」「悪用厳禁」
主な用途 :コンテンツ誘導・話題化
【希少性マーケティング】
心理の起点 :入手困難で欲しくなる
刺激する感情:競争心・先取り欲求
主な表現 :「残りわずか」「先着順」
主な用途 :販売促進・申込み促進
\ 2つを組み合わせると効果倍増 /
この2つの心理効果は、組み合わせることでさらに強力な訴求力を発揮します。
たとえば、
「今月だけ公開される悪用厳禁の裏話」
という表現は、カリギュラ効果(悪用厳禁)と希少性マーケティング(今月だけ)を同時に使っています。これにより読者の好奇心と購買・申込み意欲の両方を高めることができます。
まとめ
マーケティングにおいて人の行動を促す心理効果は多数ありますが、「禁止されると逆に見たくなる」カリギュラ効果と、「希少性が高まると欲しくなる」希少性マーケティングは、特に汎用性が高く、幅広い場面で活用できます。使いすぎに注意しながら、適切に組み合わせて活用することで、コンテンツや商品訴求の成果を大きく高めることができるでしょう。
>関連ページ
NEXT
「返報性の原理」とは?ビジネスシーンで活用する方法
BACK
「マーケティングと行動心理学 その1」