プレゼンのコツ|プレゼンで陥りやすい3つの病気と治療法

「プレゼンって、苦手…」
そう感じている方、多いのではないでしょうか?私自身もまさにその一人。学生時代の講評会からずっと、あの「みんなの視線が自分に集まる感じ」がどうにも苦手でした。
社会人になって何度かプレゼンの機会を経験してきましたが、いまだに慣れる気配はありません。
プレゼン中に「この内容、ちゃんと伝わってる?」「ていうか、みんな話聞いてる?」「もしかして寝てる?」とつい相手の反応を気にしてしまい、集中できなくなることもしばしば。
今回はそんな“伝える場”でつい陥りがちな3つの“プレゼン病”と、その治し方をご紹介します。
>第一弾 「販促企画立案|企画立案で陥りやすい3つの病気と治療法」
1. ベラベラ話しすぎ病
2. カッコつけ病
3. モジモジ病・能面病
4. プレゼンのゴールは「相手を動かすこと」
1.ベラベラ話しすぎ病
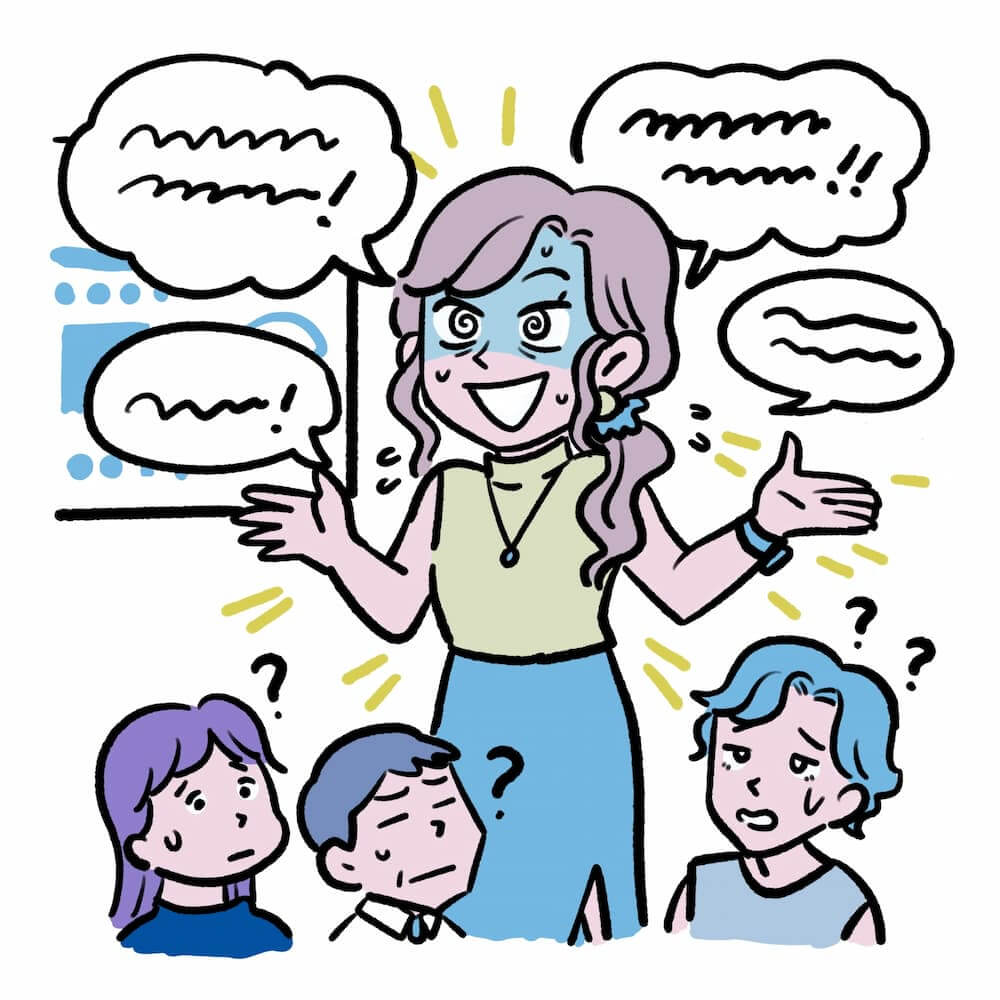
話すのが得意な人ほど発症しやすい病気。とにかくたくさん喋ってしまう状態です。
プレゼンは、打ち合わせなどと違い、相手はいますが、対話ではありません。こちらが一方的に話す時間が続くため、自分が話すのを止めれば当然沈黙が生まれます。そのため沈黙に耐えられず「何か言わなきゃ」と焦ってしまいがち。プロジェクトの内容だけでなく、頑張ったエピソードや余談までどんどん盛り込んでしまう。
聞き手は意外と冷静で、「なるほど、わかりました……で、結局何が言いたかったんですか?」という状態になりがちです。
この患者のプレゼンは、その場では一見成立しているように見えますが、結果、肝心の“伝えたいこと”が聞き手の記憶に残らない、なんてことも。
治療法:1分で結論を伝える訓練をする
プレゼンの目的は、「相手にどう動いてもらいたいか」を伝えることです。
たとえば新商品を提案する場なら、「こんな商品があります」ではなく、「だから売れます。やりましょう!」というゴールがあるはず。
その“結論”を冒頭1分で言い切る練習をしましょう。
人は他人の話の8割を聞いていない、と言われています。「いやいや、私はちゃんと話を聞いてますよ」という方もいるかもしれませんが、どんなに相手が好意的に話を聞いてくれていたとしても、自分が伝えたかったことの半分も伝わらない、と思ってプレゼンを行ってください。
8割の話を聞いておらず、理解もしてくれない、という前提で少しでも相手に印象を残すプレゼンの構成、それが“1分で伝わる内容にする”です。1分で伝わらない話は、何時間かけても伝わらない——くらいの気持ちで、構成を考えてみてください。
2. カッコつけ病

別名、「カタカナ病」です。
「コンセンサス」「アグリー」「ペンディング」……。
なんとなくビジネスっぽく聞こえる横文字、つい使っていませんか?
たとえば、
【A】「今後の方向性についてはクライアントにコンセンサスを取り、慎重に進めたく、一旦ペンディングにさせてください」
【B】「今後の方向性はお客様にも同意を得てから慎重に進めたいので、一度保留にさせてください」
これは極端な例ですが、【A】と【B】なら後者の方が意味がスッと入ってきますよね。
もともと日本語は外来語を取り入れやすい言語と言われていますが、「かっこいいから」とむやみに横文字を多用することはプレゼンでは避けましょう。
特にWEB業界や広告業界ではカタカナ語に囲まれて仕事をすることが多く、無意識にそのままプレゼンにも持ち込んでしまうことがあります。
でも、プレゼンの聞き手の「カタカナ語耐性」は人によってバラバラ。
横文字を聞きながら「それってどういう意味だっけ?」と考えている間に話がどんどん進んでしまい、結果的に理解が追いつかない……なんてことも。
治療法:中学生でもわかる言葉を選ぶ
プレゼンでは、「言葉のかっこよさ」よりも「伝わりやすさ」が命です。
カタカナ語を避け、中学生にも伝わる表現を心がけましょう。
業界用語についても同様です。「うちの業界じゃ当たり前」でも、相手にとっては未知の単語かもしれません。
本番前に、業界外の人に向けて模擬プレゼンをしてみるのもおすすめ。意味がわからない言葉はなかったか確認してみましょう。
聞き手を“迷子”にさせない、確実に理解できるやさしい言葉選びがプレゼン成功のカギです。
3. モジモジ病・能面病

恥ずかしそうに俯いて話す「モジモジ病」、無表情・無感情で話す「能面病」。
どちらも日本人に多く見られるプレゼン症状です。
日本は、人前で何かをする機会が諸外国と比べ幼少期からとても少なく、自己表現が苦手な人が多いといわれています。近年は学校教育でもプレゼンテーションを取り入れようとする動きもあるようですが、まだまだ機会が多いとは言えません。
プレゼンの中身はバッチリでも、話し手が自信なさげだったり表情が乏しかったりすると、聞き手は不安になります。
「この人、本当にこの提案に自信あるのかな……?」と思われたらもったいないですよね。
治療法:大ゲサくらいの熱量を込めて“役を演じる”
熱く語る=かっこ悪い、と思っていませんか?海外のドラマでよく見る欧米のビジネスパーソンが行うようなドラマチックなプレゼンは、日本人がやってもサムイだけ…と思ってしまっている人も多いのではないでしょうか。
でも、友達にお気に入りのドラマやライブをおすすめする時って、自然とテンションが上がって、表情も声も豊かになりますよね。
たとえばあなたの友人が、韓国ドラマやアーティストなどにドハマりして、「このドラマ、見てみてよ!めちゃくちゃ泣けるから!」や「来月このアーティストのライブがあるんだけど、一緒に行ってみない?今オススメの曲のリストLINEに送ったから聞いてみてよ!」と、キラキラとした表情で、かつ身振り手振りを交えておすすめしてきたとします。
想像してみてください。「そこまで言うなら試しに聞いてみようかな…」となりませんか?
その「熱量」がプレゼンにも必要です。
プレゼンとは、「自分の想いで相手を動かす」こと。
そのためには、少しオーバーなくらいの表情やジェスチャーで、言葉だけでなく“熱意ごと”伝えていきましょう。
とはいえ、この「モジモジ病」「能面病」には、なかなか一朝一夕で効く薬がありません。
模擬プレゼンや練習を重ね、少しずつ治療していきましょう。
4. プレゼンのゴールは「相手を動かすこと」
どれか一つでも、思い当たる「病気」はありましたか?
プレゼンの目的は、「上手に話すこと」ではなく、「相手の心を動かすこと」です。
そのために大切なのはこの3つ:
・最初の1分で、ズバッと結論を言う
・難しい言葉は使わず、中学生でもわかる表現で
・熱量を込めて、自信を持って語る
この3つをおさえれば、あなたの「伝える力」はきっと磨かれていくはずです。
おすすめの処方箋(書籍紹介)
より深く知りたい方に、プレゼンに効く一冊をご紹介します。
起業家からビジネスパーソンまで年間300人以上のプレゼンを指導した著者が、プレゼンに限らず、人前に立って話をする、指示をする、伝える、ということが苦手な方に向け、伝え方の基本と極意が詰まった本です。
■ 1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術(伊藤 羊一 著)
https://www.amazon.co.jp/dp/4797395230/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_DYKKKFR1Q01E5KY3HH7T

